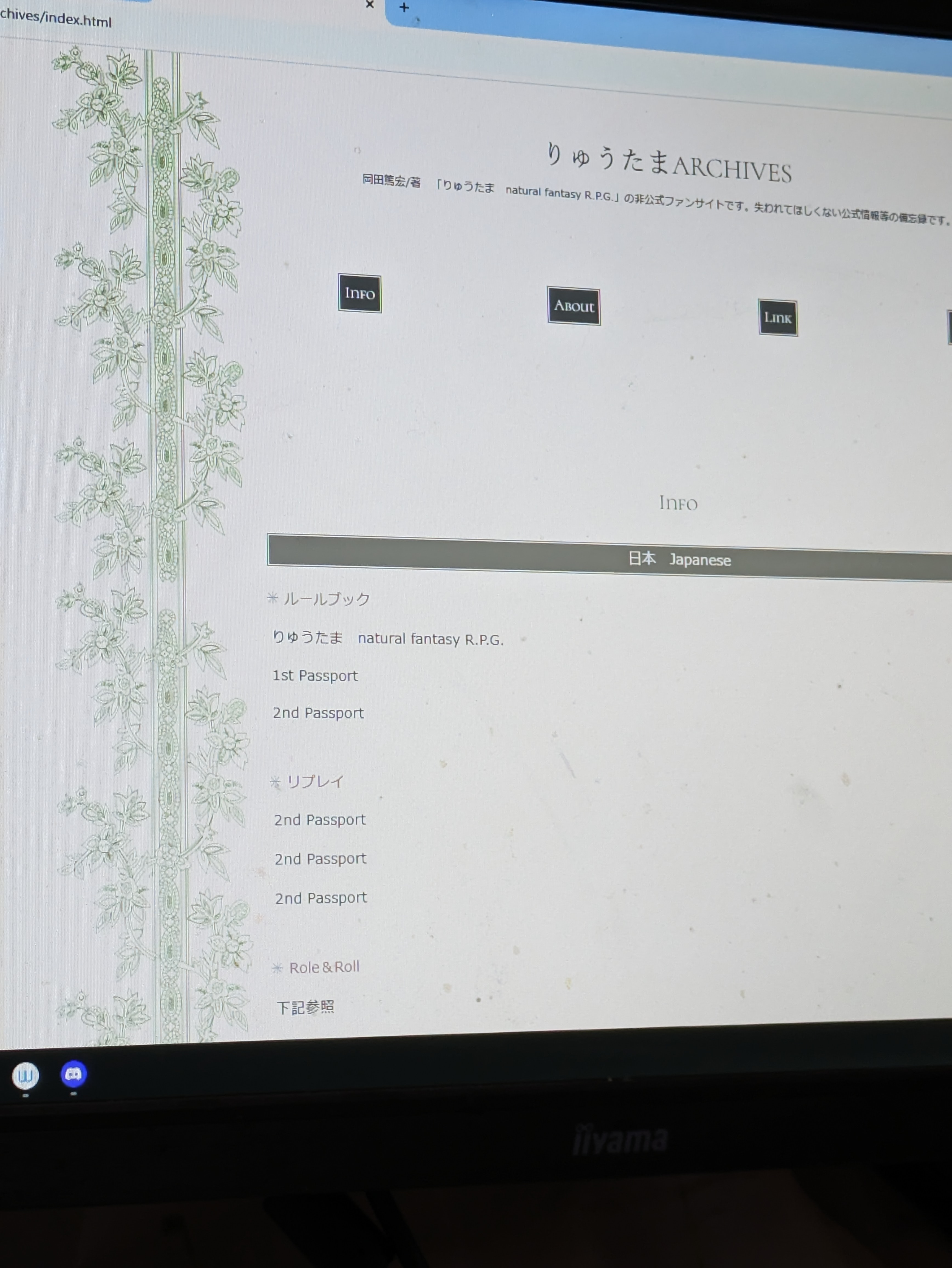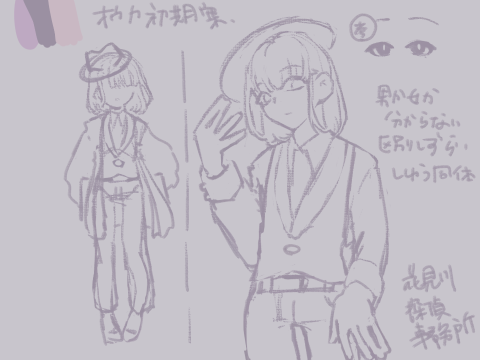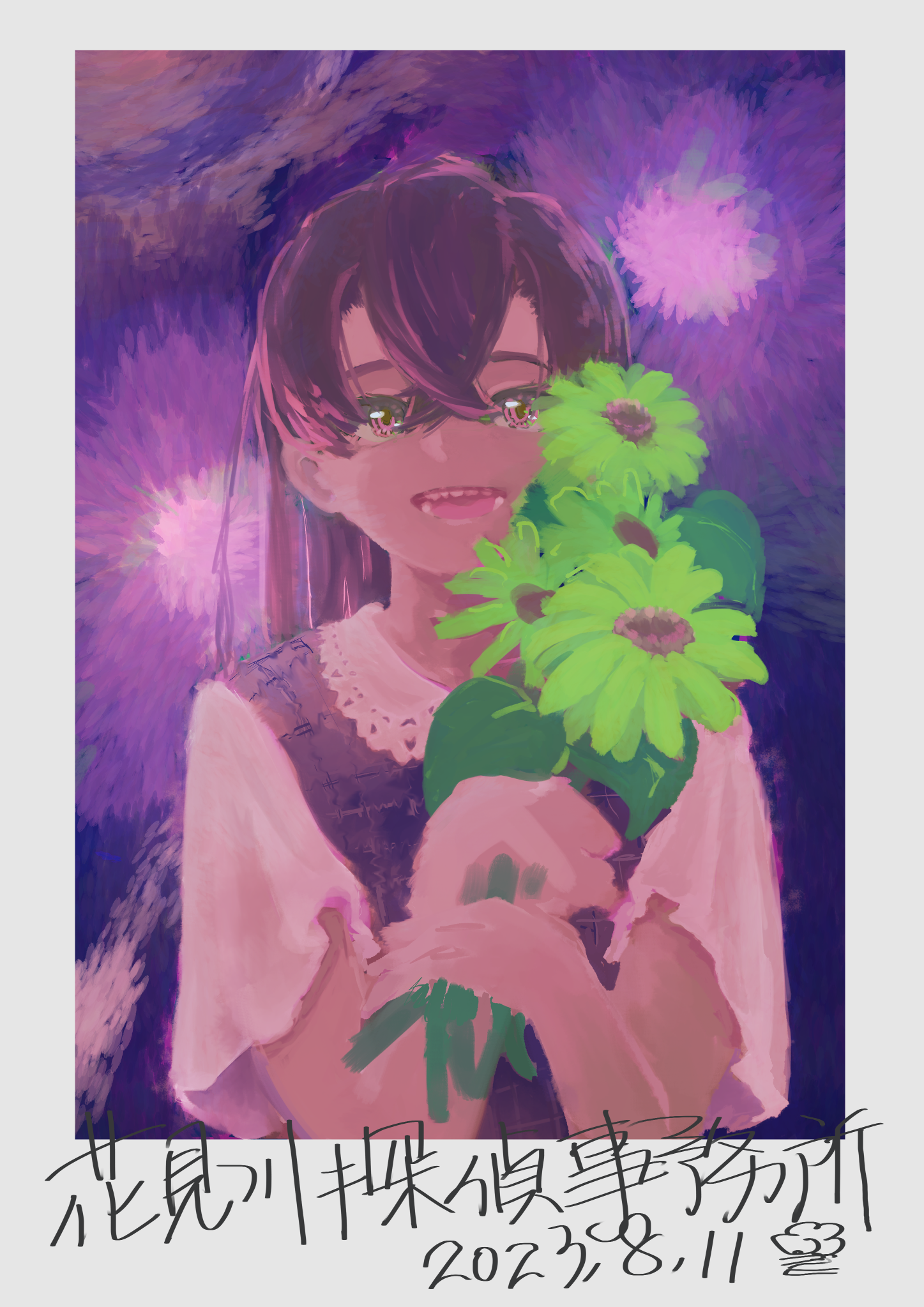No.12, No.11, No.10, No.9, No.8, No.7[6件]
test
フリーゲーム「ファミレスを享受せよ」(月刊湿地帯)
良さげなテキストアドベンチャー
https://oissisui.itch.io/moonpalace
#スクラップブック

良さげなテキストアドベンチャー
https://oissisui.itch.io/moonpalace
#スクラップブック

片栗粉、豆板醤、甜麺醤、オイスターソース、みりん
インスタント麺、ひき肉
インスタントコーヒー
#買い物
インスタント麺、ひき肉
インスタントコーヒー
#買い物
AZNANAで見るユートピア概論
#AZNANA #ゲーム #感想
AZNANAで描かれた「壁に覆われた町」は、ユートピアでしょうか?ディストピアでしょうか?
やや穿った問いではありますが、この答えを作中での描写から類推することができます。
本屋で販売される「すばらしいせかい」の元ネタは、おそらく「すばらしい新世界」です。この本の語る世界が“新”ではなくなったところに、意図を感じませんか。「壁に覆われた町」にとって、「すばらしい新世界」はもはや目新しいものでは無いのです。
なんでも屋は、「すばらしいせかい」についてこう発言します。「ディストピア小説の名作だね」と。
なんでも屋は、作中で唯一、「町」について客観的立場を取る人物です。「すばらしいせかい」が(未来のものではなく)現在のものになった「町」を、ディストピアだと風刺したのでしょうか。
しかして、一方で、「壁に覆われた町」はユートピア的要素を強く持ちます。
ユートピア的要素について、wikipediaにはこうあります。
●周囲の大陸と隔絶した孤島である。
●科学と土木によってその自然は無害かつ幾何学的に改造され、幾何学的に建設された城塞都市が中心となる。
●生活は理性により厳格に律せられ、質素で規則的で一糸乱れぬ画一的な社会である。ふしだらで豪奢な要素は徹底的にそぎ落とされている。住民の一日のスケジュールは労働・食事・睡眠の時刻などが厳密に決められている。長時間労働はせず、余った時間を科学や芸術のために使う。
●人間は機能・職能で分類される。個々人の立場は男女も含め完全に平等だが、同時に個性はない。なお、一般市民の下に奴隷や囚人を想定し、困難で危険な仕事をさせている場合がある。
●物理的にも社会的にも衛生的な場所である。黴菌などは駆除され、社会のあらゆるところに監視の目がいきわたり犯罪の起こる余地はない。
●変更すべきところがもはやない理想社会が完成したので、歴史は止まっている。ユートピアは、ユークロニア(英: uchronia, 時間のない国)でもある。
「町」と強烈に共通する点がありますね。
詳細は後述しますが、僕はこの「町」がユートピアとして非常に精巧に編まれた町だと思いました。
結論を先に申し上げます。
「壁に覆われた町」は、ユートピアを目指して生み出された町なのでしょう。それと同時に、時代の変遷によりニンゲンの価値観が変化し、ディストピアへと変貌してしまった町なのでしょう。
なぜ僕がそう考察したのか。ユートピアとは何か。この言葉の歴史を振り返りながらお話ししたいと思います。
最初に断っておきますけれど、この文章を全て精読する必要はありません。この世の文章のすべてを読もうなんて試みは、どだい無理な話ですので、読者であるあなたの興味関心が赴く部分だけ拾い読みされるくらいがちょうどいいかと思います。
ユートピアという言葉は、16世紀、敬虔なカトリック教徒にして政治家であったトマス・モアによる造語です。1516年、トマス・モアは「社会の最善政体とユートピア新島についての楽しく有益な小著」において、祖国イングランドの現状を批判しつつ、空想上の理想の国家「ユートピア」について語ります。
もちろん、トマス・モア以前にもユートピア的な空想はありました。
ユートピア(理想郷)に関する最古の記述を、「ギルガメッシュ叙事詩」に求める説があります。遅くとも紀元前2000年には成立したこの物語は、シュメール(中東のイラク南部地域)を中心に広く伝播されました。直接ユートピア(理想郷)について語られているわけではありませんが、ギルガメッシュという「理想の王」を通して、その時代・その地域の人々がどのような治世を望んだのかを断片的に垣間見ることができます。
1世紀ごろにはユダヤ教の正典・旧約聖書が成立します。この書では唯一神が統治する千年帝国の存在が説かれます。これは「ユートピア(理想郷)」の存在が示唆された最も著名な書でしょう。ユダヤ教から生まれた神の子・イエスは、信徒に「御国(千年王国)がきますように」と祈るよう説いたと言われています。全能の神による統治を迎合する理想郷論は、19世紀後半にアメリカで起こったキリスト教系の新宗派エホバの証人によって大きく取り沙汰されることになります。(もっと深堀したいところですが、キリスト教の宗派に関する議論はいろいろな人に怒られそうなので、これ以上の言及は控えます。)
4世紀には「桃花源記」が成立し、中国文化圏におけるユートピア・理想郷の代名詞として「桃源郷」の概念が広まります。桃源郷は政治思想というよりは現実逃避の娯楽小説という側面が強いものの、思想成立の初期の多く見られる牧歌的理想郷について語られている点で興味深いです。
さらに時代は下って12世紀、プレスター・ジョン伝説が欧州で大流行します。これはプレスター・ジョンという男がイスラーム教徒を撃退し、キリスト教国をチベット(またはアジアのどこか、もしくはアフリカ)に建国したという伝説です。12世紀は第二次・第三次十字軍遠征が行われた時代で、キリスト教国とイスラーム強国による聖地エルサレムの争奪戦が繰り広げられた時代です。キリスト教徒が空想した、信仰の都。これをプレスター・ジョン伝説に見ることができます。
話をユートピアに戻しましょう。
トマス・モアが偉大であった点は、この空想の理想郷「ユートピア」について、その暮らしのみならず社会構造まで語って見せた点です。この衝撃と目新しさが、16世紀ルネサンスという時代で爆発的に話題になり、「ユートピア」という概念が語り継がれる一要素になりました。
16世紀というのは、現代人である我々からすると、まだまだ野蛮で不平等な時代です。この時代のヨーロッパ世界のことを、侮辱的に「暗黒時代」と呼称する大衆小説も多くあります。貴族と宗教家が権力と富を独占した一方で、多くの民衆は暴力と飢餓におびえていました。盗人が出ても、それを検挙する警察組織さえまだありませんので、地元住人たちによる小規模な自治組織があったりなかったり、罪人の家を一方的に打ち壊したりといった感じです。
また、ローマ・カトリック教会が組織的に腐敗しきっていた時期で、例えば免罪符の販売が宗教的権力者の財源の一つになっていました。
世界史的には、列強(主としてスペイン)による新大陸の征服(コンキスタドール)がどんどん進行し、中南米地域の先住文明が多く滅びました。
日本も例外ではなく争いの時代、戦国時代の真っただ中です。
そんな時代で、トマス・モアはどんなユートピア 理想郷を思い描いたのでしょうか。
市民はみな平等で、貧富の差も無い。
労働は一日6時間。失業は根絶されている。
休日は精神の自由な活動と教養の習得に充てられる。
医療費は無料。安楽死も認められている。
複数の宗教があり、信仰の自由がある。
思わずうなりたくなるほどの理想国家ではありますが、こう表現したら、あなたはどう思うでしょう?
女性による男性への奉仕や、奴隷が奨励されている。
婚前交渉と離婚は禁止。
私有財産は無い。必要なものは共有倉庫で管理される。
化粧、贅沢、賭博は忌避される。
市民全員が同じデザインのシンプルな服を着る。
市民が黄金を嫌悪するよう、刷り込みが行われている。
食事は配給制。
旅行するためには許可証が必要。
無神論者は軽蔑される。
自ら命を絶った者は宗教的に忌まれ、泥沼に遺体を放り出される。
家に鍵は無く、戸は指で押せば開く。
これのどこが理想国家なんだ、と文句をつけたくなりますね。徹底された社会主義のかおりを感じます。私たちは歴史的に社会主義(共産主義、全体主義)が「失敗」したことを知っています。しかし、トマス・モアの生きた16世紀は、まだマルクスさえ生まれていません。
トマスが信仰したキリスト教の聖書に、こんな文言があります。
「信者たちはみな一緒にいて、いっさいの物を共有にし、
資産や持ち物を売っては、必要に応じてみんなの者に分け与えた。」(使徒言行録 2:44-45)
使徒言行録(Acts of the Apostles.使徒行伝、初代教会の働きとも。邦訳は多くの表記ゆれがあります)は新約聖書の一書であり、西暦61年から64年の間に書かれたと伝承されています。四福音書に次いで収録された、由緒ある文書です。使徒パウロの一行の滅私奉公な、あるいは社会主義的な行いを「善行」ととらえている様子が見て取れます。
また、それよりも古い古代ギリシャの哲学者・プラトンは「民主政治は衆愚政治をもたらす」として、原始共産制的階級社会を国家の理想として語っています。(プラトンの「国家論」は大長編であるうえ、時代によって解釈が変遷してきた歴史があるので、内容の解説は他の有識者にゆだねようと思います。)
教養深いトマス・モアだからこそ、当時の階級社会を嫌悪し、こういった先人たちの「理想国家」に共感したのかもしれませんね。
活版印刷の輸入によって書が娯楽へと零落したこと、そして15世紀ルネサンスという時代であったこともあり、「社会の最善政体とユートピア新島についての楽しく有益な小著」は大きな反響を呼びました。これに触発されて、数々のユートピア小説が発表されます。例をあげればキリがありませんが、日本ではジョナサン・スウィフトの「ガリヴァー旅行記」が有名だと思います。「天空の城ラピュタ」の着想元のひとつですね。
19世紀資本主義が勃興してからは、それに対抗するように社会主義や共産主義を理想とする小説が多く、あまりにも多く出版されるようになります。この時代、一時は娯楽となったユートピア小説が、再び政治の色をにじませるようになりました。
社会学者カール・マンハイムは著書「イデオロギーとユートピア」(1929年)において、個人の「認識」は、歴史やその人の社会的立場に拘束されると説きました。「一見すると客観的で中立的な言明であっても、社会による思想の拘束を逃れられない」という意見です。カール・マンハイムはこれを存在拘束性と名付けました。
イデオロギーは、支配階級が支配を継続するために不都合な現実を直視しないという傾向。ユートピアは、革命家たちが革命を行うために不都合な現実を直視しないという傾向。
この二つは似た傾向を持ちますが、決定的に違う側面があります。ユートピアは実現しうるのです。イデオロギーは「既にそうであるものの正当化」ですので、視線は過去に向いており、問題解決に向けたエネルギーを持ちません。一方で、ユートピアは視線が未来に向いていますので、「既にそうであるもの」を破壊するエネルギーを持ちます。これは秩序の破壊と同義ですが、この破壊を行う際、一時だけであろうとも、ユートピアは存在しうるのです。
また、イデオロギーとユートピアは、ともに「正しい現実を認識できない」という点で共通しています。この世に社会を正しく認識できる人物は存在しえないのでしょうか?
この課題を乗り越えられる可能性があるとすれば、それは、「自由に浮動するインテリゲンツィア」です。社会階級とは無関係に行動することができ、社会を多面的に認識することができる教養人たちのことをいいます。そして、真理=理想の社会に到達しうる「自由に浮動するインテリゲンツィア」が政治を把握することが望ましい…、とカール・マンハイムは語りました。
(知識社会学は、正直なところ門外漢ですので、解釈の間違いなどがありましたらどんどんご指摘いただければ幸いです。)
カール・マンハイムが夢見たユートピア。階級に縛られない、思想に縛られない、知識あるものによる政治。これが、2000年代ディストピアものによって、AIによる支配という形で物語られているという点は非常に興味深いです。
閑話休題。
では、ディストピアという概念はいつから生まれたのでしょうか。
ユートピア小説と同じく、ディストピア小説も、また、未来へと視線が向く傾向があります。ユートピアが「実現可能な、そして理想の社会」であるなら、ディストピアは「実現可能な、しかし最悪の社会」です。全く正反対のようでありながら、架空の社会によって現在の社会を批判しているという点で共通します。
「イデオロギーとユートピア」と時期を同じくして、1932年、世界恐慌の真っただ中で、ディストピア小説の傑作「すばらしい新世界」が発表されます。
1945年から1989年の期間は、いわゆる冷戦の時代です。第二次世界大戦で大きな損害を被ったヨーロッパ諸国にとって、スターリン全盛期のソ連は、思想的にも軍事力的にも脅威でした。そこで登場するのが、すっかり世界の超大国へと成長したアメリカです。軍事力・経済力共に申し分ありませんし、二度の世界大戦を経てなお、本土を無傷に保っていました。
そして1947年3月12日、当時の米国大統領ハリー・S・トルーマンによる演説(トルーマン・ドクトリン)を以て東西の決裂は決定的となります。東西各国は技術力で、あるいは印象操作で、はたまた代理戦争で、敵国を貶めてやろうという風潮が高まっていきます。
1949年に発表された「1984」は、ある意味その典型例と言えるでしょう。この作品は、一党独裁によって個人の思想が管理・統制され、党(全体)のための奉仕を強要されるという反ユートピア、つまりディストピアを主題に描かれました。元来オーウェンは反全体主義の思想を持っていましたが、「1984」発表においては、この小説が政権批判のためではないと明言していたようです。ですが…実際は、冷戦の冷え込みと共にに大流行し、反共のバイブルとして愛読されることになります。
その後の顛末は、皆さんご存じのとおりです。ソヴィエトロシアは打倒されました。残った中国・ベトナム・キューバなどの社会主義国も、政治的には社会主義を維持しつつ、市場経済には資本主義を導入しています。世界は19世紀に敷かれた資本主義のレールの上を走っています。この世界を糾弾するわけではありませんが、資本主義社会は現在に至るまで「共産主義は悪」という印象を市民に植え付けることに成功しているというただ一点が恐ろしいです。
長くなってしまいましたが、これがひとつの夢の終わり、僕の考察した「ユートピア」の概論です。
本来であれば古代文明における政治の如何や、アメリカ大陸の開拓も語りたかったのですが、それはさすがに話の収拾がつかないので割愛しました。概論を謳いながらも一意的なお話となってしまい、申し訳ありません。
最後に、簡単に僕の感想を述べて終わりにしたいと思います。
ユートピアとは、規定された一個の理想社会のことではない、というのが僕の持論です。ユートピアとディストピアは、いわば卵と鶏。どちらともなく生まれ、打倒され、また生まれ。歴史とともに変化し、人類文明とともに成長してきた概念とも解釈できます。
かつてユートピアだった「壁に覆われた町」。すでにディストピアへと変貌してしまったこの「町」は、卵の殻をやぶり、「町の外」という理想郷…ユートピアを夢想するようになりました。
「町の外」というユートピアがディストピアへと変貌することはあるのでしょうか。そのとき、「壁に覆われた町」はどのように扱われるのでしょうか。
人々がユートピアを追い求める気持ちを忘れてしまいませんように。少年とアズナナが、きっと幸せを掴みとりますように。そう願ってやみません。
畳む
#AZNANA #ゲーム #感想
AZNANAで描かれた「壁に覆われた町」は、ユートピアでしょうか?ディストピアでしょうか?
やや穿った問いではありますが、この答えを作中での描写から類推することができます。
本屋で販売される「すばらしいせかい」の元ネタは、おそらく「すばらしい新世界」です。この本の語る世界が“新”ではなくなったところに、意図を感じませんか。「壁に覆われた町」にとって、「すばらしい新世界」はもはや目新しいものでは無いのです。
なんでも屋は、「すばらしいせかい」についてこう発言します。「ディストピア小説の名作だね」と。
なんでも屋は、作中で唯一、「町」について客観的立場を取る人物です。「すばらしいせかい」が(未来のものではなく)現在のものになった「町」を、ディストピアだと風刺したのでしょうか。
しかして、一方で、「壁に覆われた町」はユートピア的要素を強く持ちます。
ユートピア的要素について、wikipediaにはこうあります。
●周囲の大陸と隔絶した孤島である。
●科学と土木によってその自然は無害かつ幾何学的に改造され、幾何学的に建設された城塞都市が中心となる。
●生活は理性により厳格に律せられ、質素で規則的で一糸乱れぬ画一的な社会である。ふしだらで豪奢な要素は徹底的にそぎ落とされている。住民の一日のスケジュールは労働・食事・睡眠の時刻などが厳密に決められている。長時間労働はせず、余った時間を科学や芸術のために使う。
●人間は機能・職能で分類される。個々人の立場は男女も含め完全に平等だが、同時に個性はない。なお、一般市民の下に奴隷や囚人を想定し、困難で危険な仕事をさせている場合がある。
●物理的にも社会的にも衛生的な場所である。黴菌などは駆除され、社会のあらゆるところに監視の目がいきわたり犯罪の起こる余地はない。
●変更すべきところがもはやない理想社会が完成したので、歴史は止まっている。ユートピアは、ユークロニア(英: uchronia, 時間のない国)でもある。
「町」と強烈に共通する点がありますね。
詳細は後述しますが、僕はこの「町」がユートピアとして非常に精巧に編まれた町だと思いました。
結論を先に申し上げます。
「壁に覆われた町」は、ユートピアを目指して生み出された町なのでしょう。それと同時に、時代の変遷によりニンゲンの価値観が変化し、ディストピアへと変貌してしまった町なのでしょう。
なぜ僕がそう考察したのか。ユートピアとは何か。この言葉の歴史を振り返りながらお話ししたいと思います。
最初に断っておきますけれど、この文章を全て精読する必要はありません。この世の文章のすべてを読もうなんて試みは、どだい無理な話ですので、読者であるあなたの興味関心が赴く部分だけ拾い読みされるくらいがちょうどいいかと思います。
ユートピアという言葉は、16世紀、敬虔なカトリック教徒にして政治家であったトマス・モアによる造語です。1516年、トマス・モアは「社会の最善政体とユートピア新島についての楽しく有益な小著」において、祖国イングランドの現状を批判しつつ、空想上の理想の国家「ユートピア」について語ります。
もちろん、トマス・モア以前にもユートピア的な空想はありました。
ユートピア(理想郷)に関する最古の記述を、「ギルガメッシュ叙事詩」に求める説があります。遅くとも紀元前2000年には成立したこの物語は、シュメール(中東のイラク南部地域)を中心に広く伝播されました。直接ユートピア(理想郷)について語られているわけではありませんが、ギルガメッシュという「理想の王」を通して、その時代・その地域の人々がどのような治世を望んだのかを断片的に垣間見ることができます。
1世紀ごろにはユダヤ教の正典・旧約聖書が成立します。この書では唯一神が統治する千年帝国の存在が説かれます。これは「ユートピア(理想郷)」の存在が示唆された最も著名な書でしょう。ユダヤ教から生まれた神の子・イエスは、信徒に「御国(千年王国)がきますように」と祈るよう説いたと言われています。全能の神による統治を迎合する理想郷論は、19世紀後半にアメリカで起こったキリスト教系の新宗派エホバの証人によって大きく取り沙汰されることになります。(もっと深堀したいところですが、キリスト教の宗派に関する議論はいろいろな人に怒られそうなので、これ以上の言及は控えます。)
4世紀には「桃花源記」が成立し、中国文化圏におけるユートピア・理想郷の代名詞として「桃源郷」の概念が広まります。桃源郷は政治思想というよりは現実逃避の娯楽小説という側面が強いものの、思想成立の初期の多く見られる牧歌的理想郷について語られている点で興味深いです。
さらに時代は下って12世紀、プレスター・ジョン伝説が欧州で大流行します。これはプレスター・ジョンという男がイスラーム教徒を撃退し、キリスト教国をチベット(またはアジアのどこか、もしくはアフリカ)に建国したという伝説です。12世紀は第二次・第三次十字軍遠征が行われた時代で、キリスト教国とイスラーム強国による聖地エルサレムの争奪戦が繰り広げられた時代です。キリスト教徒が空想した、信仰の都。これをプレスター・ジョン伝説に見ることができます。
話をユートピアに戻しましょう。
トマス・モアが偉大であった点は、この空想の理想郷「ユートピア」について、その暮らしのみならず社会構造まで語って見せた点です。この衝撃と目新しさが、16世紀ルネサンスという時代で爆発的に話題になり、「ユートピア」という概念が語り継がれる一要素になりました。
16世紀というのは、現代人である我々からすると、まだまだ野蛮で不平等な時代です。この時代のヨーロッパ世界のことを、侮辱的に「暗黒時代」と呼称する大衆小説も多くあります。貴族と宗教家が権力と富を独占した一方で、多くの民衆は暴力と飢餓におびえていました。盗人が出ても、それを検挙する警察組織さえまだありませんので、地元住人たちによる小規模な自治組織があったりなかったり、罪人の家を一方的に打ち壊したりといった感じです。
また、ローマ・カトリック教会が組織的に腐敗しきっていた時期で、例えば免罪符の販売が宗教的権力者の財源の一つになっていました。
世界史的には、列強(主としてスペイン)による新大陸の征服(コンキスタドール)がどんどん進行し、中南米地域の先住文明が多く滅びました。
日本も例外ではなく争いの時代、戦国時代の真っただ中です。
そんな時代で、トマス・モアはどんなユートピア 理想郷を思い描いたのでしょうか。
市民はみな平等で、貧富の差も無い。
労働は一日6時間。失業は根絶されている。
休日は精神の自由な活動と教養の習得に充てられる。
医療費は無料。安楽死も認められている。
複数の宗教があり、信仰の自由がある。
思わずうなりたくなるほどの理想国家ではありますが、こう表現したら、あなたはどう思うでしょう?
女性による男性への奉仕や、奴隷が奨励されている。
婚前交渉と離婚は禁止。
私有財産は無い。必要なものは共有倉庫で管理される。
化粧、贅沢、賭博は忌避される。
市民全員が同じデザインのシンプルな服を着る。
市民が黄金を嫌悪するよう、刷り込みが行われている。
食事は配給制。
旅行するためには許可証が必要。
無神論者は軽蔑される。
自ら命を絶った者は宗教的に忌まれ、泥沼に遺体を放り出される。
家に鍵は無く、戸は指で押せば開く。
これのどこが理想国家なんだ、と文句をつけたくなりますね。徹底された社会主義のかおりを感じます。私たちは歴史的に社会主義(共産主義、全体主義)が「失敗」したことを知っています。しかし、トマス・モアの生きた16世紀は、まだマルクスさえ生まれていません。
トマスが信仰したキリスト教の聖書に、こんな文言があります。
「信者たちはみな一緒にいて、いっさいの物を共有にし、
資産や持ち物を売っては、必要に応じてみんなの者に分け与えた。」(使徒言行録 2:44-45)
使徒言行録(Acts of the Apostles.使徒行伝、初代教会の働きとも。邦訳は多くの表記ゆれがあります)は新約聖書の一書であり、西暦61年から64年の間に書かれたと伝承されています。四福音書に次いで収録された、由緒ある文書です。使徒パウロの一行の滅私奉公な、あるいは社会主義的な行いを「善行」ととらえている様子が見て取れます。
また、それよりも古い古代ギリシャの哲学者・プラトンは「民主政治は衆愚政治をもたらす」として、原始共産制的階級社会を国家の理想として語っています。(プラトンの「国家論」は大長編であるうえ、時代によって解釈が変遷してきた歴史があるので、内容の解説は他の有識者にゆだねようと思います。)
教養深いトマス・モアだからこそ、当時の階級社会を嫌悪し、こういった先人たちの「理想国家」に共感したのかもしれませんね。
活版印刷の輸入によって書が娯楽へと零落したこと、そして15世紀ルネサンスという時代であったこともあり、「社会の最善政体とユートピア新島についての楽しく有益な小著」は大きな反響を呼びました。これに触発されて、数々のユートピア小説が発表されます。例をあげればキリがありませんが、日本ではジョナサン・スウィフトの「ガリヴァー旅行記」が有名だと思います。「天空の城ラピュタ」の着想元のひとつですね。
19世紀資本主義が勃興してからは、それに対抗するように社会主義や共産主義を理想とする小説が多く、あまりにも多く出版されるようになります。この時代、一時は娯楽となったユートピア小説が、再び政治の色をにじませるようになりました。
社会学者カール・マンハイムは著書「イデオロギーとユートピア」(1929年)において、個人の「認識」は、歴史やその人の社会的立場に拘束されると説きました。「一見すると客観的で中立的な言明であっても、社会による思想の拘束を逃れられない」という意見です。カール・マンハイムはこれを存在拘束性と名付けました。
イデオロギーは、支配階級が支配を継続するために不都合な現実を直視しないという傾向。ユートピアは、革命家たちが革命を行うために不都合な現実を直視しないという傾向。
この二つは似た傾向を持ちますが、決定的に違う側面があります。ユートピアは実現しうるのです。イデオロギーは「既にそうであるものの正当化」ですので、視線は過去に向いており、問題解決に向けたエネルギーを持ちません。一方で、ユートピアは視線が未来に向いていますので、「既にそうであるもの」を破壊するエネルギーを持ちます。これは秩序の破壊と同義ですが、この破壊を行う際、一時だけであろうとも、ユートピアは存在しうるのです。
また、イデオロギーとユートピアは、ともに「正しい現実を認識できない」という点で共通しています。この世に社会を正しく認識できる人物は存在しえないのでしょうか?
この課題を乗り越えられる可能性があるとすれば、それは、「自由に浮動するインテリゲンツィア」です。社会階級とは無関係に行動することができ、社会を多面的に認識することができる教養人たちのことをいいます。そして、真理=理想の社会に到達しうる「自由に浮動するインテリゲンツィア」が政治を把握することが望ましい…、とカール・マンハイムは語りました。
(知識社会学は、正直なところ門外漢ですので、解釈の間違いなどがありましたらどんどんご指摘いただければ幸いです。)
カール・マンハイムが夢見たユートピア。階級に縛られない、思想に縛られない、知識あるものによる政治。これが、2000年代ディストピアものによって、AIによる支配という形で物語られているという点は非常に興味深いです。
閑話休題。
では、ディストピアという概念はいつから生まれたのでしょうか。
ユートピア小説と同じく、ディストピア小説も、また、未来へと視線が向く傾向があります。ユートピアが「実現可能な、そして理想の社会」であるなら、ディストピアは「実現可能な、しかし最悪の社会」です。全く正反対のようでありながら、架空の社会によって現在の社会を批判しているという点で共通します。
「イデオロギーとユートピア」と時期を同じくして、1932年、世界恐慌の真っただ中で、ディストピア小説の傑作「すばらしい新世界」が発表されます。
1945年から1989年の期間は、いわゆる冷戦の時代です。第二次世界大戦で大きな損害を被ったヨーロッパ諸国にとって、スターリン全盛期のソ連は、思想的にも軍事力的にも脅威でした。そこで登場するのが、すっかり世界の超大国へと成長したアメリカです。軍事力・経済力共に申し分ありませんし、二度の世界大戦を経てなお、本土を無傷に保っていました。
そして1947年3月12日、当時の米国大統領ハリー・S・トルーマンによる演説(トルーマン・ドクトリン)を以て東西の決裂は決定的となります。東西各国は技術力で、あるいは印象操作で、はたまた代理戦争で、敵国を貶めてやろうという風潮が高まっていきます。
1949年に発表された「1984」は、ある意味その典型例と言えるでしょう。この作品は、一党独裁によって個人の思想が管理・統制され、党(全体)のための奉仕を強要されるという反ユートピア、つまりディストピアを主題に描かれました。元来オーウェンは反全体主義の思想を持っていましたが、「1984」発表においては、この小説が政権批判のためではないと明言していたようです。ですが…実際は、冷戦の冷え込みと共にに大流行し、反共のバイブルとして愛読されることになります。
その後の顛末は、皆さんご存じのとおりです。ソヴィエトロシアは打倒されました。残った中国・ベトナム・キューバなどの社会主義国も、政治的には社会主義を維持しつつ、市場経済には資本主義を導入しています。世界は19世紀に敷かれた資本主義のレールの上を走っています。この世界を糾弾するわけではありませんが、資本主義社会は現在に至るまで「共産主義は悪」という印象を市民に植え付けることに成功しているというただ一点が恐ろしいです。
長くなってしまいましたが、これがひとつの夢の終わり、僕の考察した「ユートピア」の概論です。
本来であれば古代文明における政治の如何や、アメリカ大陸の開拓も語りたかったのですが、それはさすがに話の収拾がつかないので割愛しました。概論を謳いながらも一意的なお話となってしまい、申し訳ありません。
最後に、簡単に僕の感想を述べて終わりにしたいと思います。
ユートピアとは、規定された一個の理想社会のことではない、というのが僕の持論です。ユートピアとディストピアは、いわば卵と鶏。どちらともなく生まれ、打倒され、また生まれ。歴史とともに変化し、人類文明とともに成長してきた概念とも解釈できます。
かつてユートピアだった「壁に覆われた町」。すでにディストピアへと変貌してしまったこの「町」は、卵の殻をやぶり、「町の外」という理想郷…ユートピアを夢想するようになりました。
「町の外」というユートピアがディストピアへと変貌することはあるのでしょうか。そのとき、「壁に覆われた町」はどのように扱われるのでしょうか。
人々がユートピアを追い求める気持ちを忘れてしまいませんように。少年とアズナナが、きっと幸せを掴みとりますように。そう願ってやみません。
畳む
ふみさんです